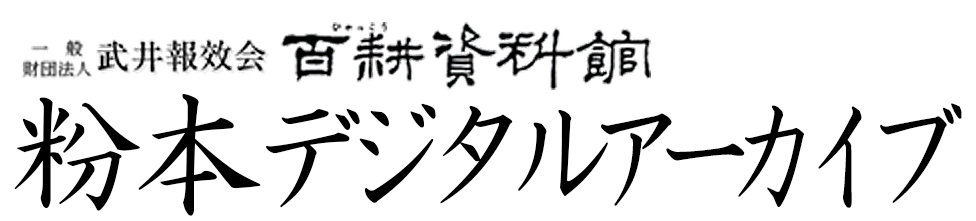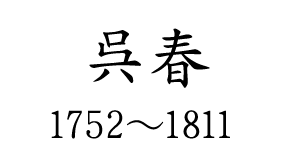 |
呉春(1752~1811)は、俗姓は松村氏。名を豊昌。通称を文蔵、嘉左衛門。京都金座役人の出身で、はじめ大西酔月(生没年不詳)に師事、その後与謝蕪村に入門して俳諧と画を学び、特に画で優れた作品を生み出しました。俳号を月渓、画号は可転、孫石、存允白などを用いましたが、天明元年(1781)12月、摂津池田(現大阪府池田市)に移り住み、翌2年正月にこの地にちなみ呉春と改めました。蕪村の没後、円山応挙門に入り、応挙の写生画法に蕪村由来の洒落な文芸趣味を加えて情趣化した作品で世評を集めました。晩年京都四条富小路(現京都市中京区)に住み、多くの弟子を輩出したことから、呉春に始まる流れを四条派と呼びます。 |
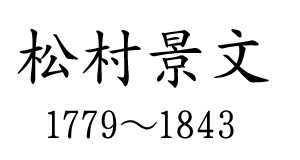 |
松村景文(1779~1843)は、名は直二のち景文。字は士藻。号は華渓。通称は要人。呉春の異母弟で、若年から画家としての教育を受けました。画題は豊富で、とりわけ花鳥画を得意としており、瀟洒な花鳥風詠の世界を色彩豊かに表現した作品が多く見られます。景文は、呉春が確立した、写生画に洒脱な情趣を加えた四条派の画風の大成者といわれ、呉春没後は岡本豊彦とともに四条派の発展に大きく貢献しました。 |
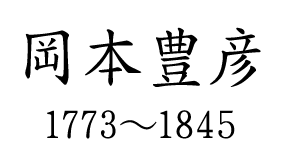 |
岡本豊彦(1773~1845)は、字は子彦。号は鯉喬、丹岳、葒村、澄神斎など。通称は司馬。俗名は幸平。豊彦は名。備中窪屋郡水江村(現岡山県倉敷市)の富裕な旧家の庶子で、十代半ば、玉島(同)の文人画家黒田綾山に師事。大坂に出て、綾山の師にあたる文人画家の福原五岳に学んだのち上京し、呉春の門に入りました。特に文人画風の山水画を得意とし、四条派の双璧として松村景文と並び称され、呉春没後の派の発展に大きく貢献しました。 |
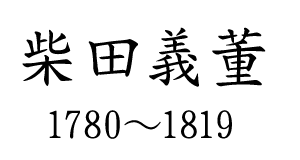 |
柴田義董(1780~1819)は、字は威仲。通称は喜太郎。号は琴江、琴渚。義董は名。備前邑久郡尻海村(現岡山県瀬戸内市)の廻船業者奥屋十兵衛慰徳の子。少年時より上洛して呉春に学び、若くして四条派の画技を極めました。特に人物画を得意とし、(松村)景文の花鳥、(岡本)豊彦の山水、義董の人物と並び称されました。 |
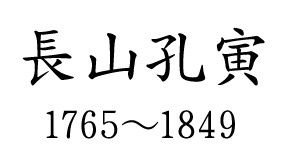 |
長山孔寅(1765~1849)は、字は士亮あるいは子亮。通称は源七郎。号は紅園、五嶺、牧斎。孔寅は名。出羽国仙北郡(現秋田県内)出身で、京都に出て呉春に師事し、のち大坂に移り住み、森徹山、中井藍江などと画名を競ったといわれます。その画風は呉春の筆法を踏まえたもので、人物画・花鳥画を得意としました。また、画家として活躍する一方で、三条茂佐彦・是福庵の名で狂歌もよくしました。『狂歌五百題集』や戯作『勧善懲悪頓着物語』などの著作が残されています。 |
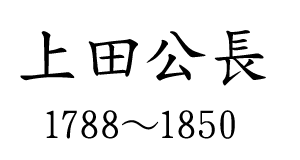 |
上田公長(1788~1850)は、名は公長。字は有秋。号は雍洲、水雲閑人。通称順蔵。大坂の人。出自には諸説あり、師弟関係についても、呉春に師事したとも、松村景文あるいは長山孔寅に学んだともいわれます。また、紀州徳川家に召されて御用絵師となり、第12代将軍家慶の前で御前揮毫したとも伝えられます。版本も多く手がけ、『公長画譜』『公長画譜二編』『水雲略画』などの画譜類を刊行したほか、地誌『紀伊国名所図会』の挿絵も描いています。四条派の流れを汲む幕末大坂画壇の一奇才と評価されています。 |
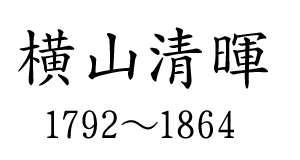 |
横山清暉(1792~1864)は、名は清暉、暉三。字は成文。通称は主馬、詳介。号は吾岳、霞城、奇文。京都の人。はじめ呉春、のち松村景文に師事しました。景文の一番弟子で、塩川文麟とともに幕末の四条派を代表し、円山派の中島来章、岸派の岸連山とあわせて幕末画壇の平安四名家とされています。その作風は景文の瀟洒な作風を受け継ぐとともに、装飾性を強調した作品も認められることが指摘されています。 |
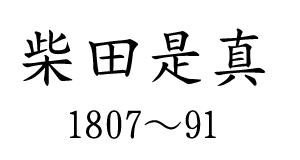 |
柴田是真(1807~91)は、幼名亀太郎、通称は順蔵、字は儃然。27歳ころから是真と号しました。別号は令哉、対柳居。江戸の人。父は装飾彫刻を手がける宮彫師。11歳で江戸の蒔絵師古満寛哉に蒔絵を学び、16歳で円山派の鈴木南嶺、のち上京して岡本豊彦に絵を学びました。以後、絵画、蒔絵、漆絵を手がけ、斬新で機知に富んだ作品を残しています。蒔絵や漆絵では、弘化2年(1845)に青海波塗を復活させたのを始め、新しい漆塗法を工夫。内外の博覧会に出品して好評を博しました。 |
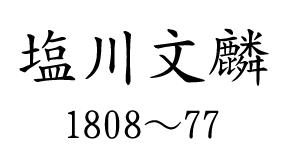 |
塩川文麟(1808~77)は、名は隼人。字は子温、子文。号は文麟、士温、雲章、木仏道人、可竹斎、泉章。通称は図書。京都の人。当初鷹司家、のちに安井宮蓮華光院門跡に仕えた父のもとに生まれ、同門跡の計らいで岡本豊彦に師事。また中国の山水画も学び、文人画の精神性を四条派の作風に取り入れました。安政2年(1855)の御所造営に参加し、障壁画を制作しています。師岡本豊彦没後から明治にかけての四条派を代表する画家で、幕末には、同門の横山清暉、円山派の中島来章、岸派の岸連山とともに平安四名家の一人に挙げられています。 |
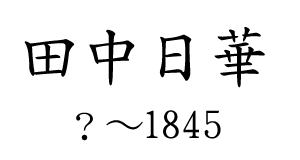 |
田中日華(?~1845)は、字は伯暉。通称は辨二。号は月渚、九峰堂。日華は名。京都の人。岡本豊彦の高弟で、豊彦譲りの山水画を遺しています。作風は師風をより繊細な感覚で描写する傾向があるとされています。生存中は、京都で刊行された文化人名録『平安人物志』にも掲載され、同流の横山清暉と並んで評価されるなど、知名の画家だったようですが、現在はあまり研究が進んでいません。 |
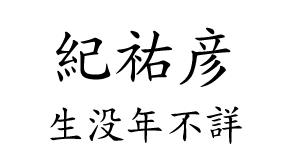 |
紀祐彦(生没年不詳)については、くわしい伝記は不明ですが、当館の粉本を収集した武井伊右衛門(1845~1917)が晩年に記した回顧録の第20巻の記事によれば、岡本豊彦の弟子であったらしいことがわかります。伊右衛門はその妻で、当時板宿村(現神戸市須磨区)の神社に年に3~5回祈祷に訪れていた相模という巫女と懇意になり、所蔵の粉本を譲り受けました。本デジタルアーカイブ収載の作品のうちに、紀祐彦が豊彦の画を模写した画を多数確認することができます。 |
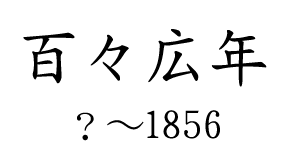 |
百々広年(?~1856)は、字は永夫、号は菱華・百錬。絵を呉春の弟子にあたる四条派の山脇東暉(紀広成とも)に学びました。作品はそれほど残っていませんが、花鳥画や山水画が見られます。狂歌本や薬学書の挿絵なども手がけ、京都で刊行された文化人名録『平安人物志』や画家の人名録『皇都書画人名録』にも登場することから、当時は知名の人であったと考えられます。また、当館の粉本を収集した武井伊右衛門(1845~1917)が晩年に記した回顧録の第20巻の記事によれば、広年は一時期兵庫津(現神戸市兵庫区)に居住していたようです。 |
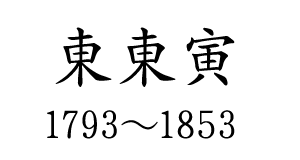 |
東東寅(1793~1853)は、字は木星、号は長月。通称は俊次。仙台出身で、はじめ狩野派の画を学び、のちに京都に上って四条派の画を学んだ東東洋(1755~1839)の長男。木挽町狩野家の照信と父に絵を学び京都で活躍しました。花鳥・人物画にすぐれました。 |
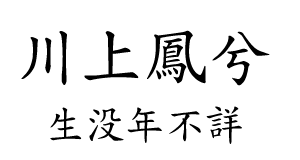 |
川上鳳兮(生没年不詳)は西宮の人。名は都澄、俗称は藤助。号は鳳兮、墨戯堂。上田公長の門に学び、山水花鳥を描きました。天保頃(1830~44)の活躍といわれますが、詳しい経歴は不明です。 |
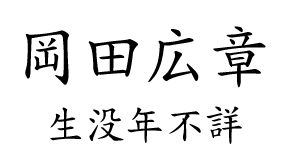 |
岡田広章(生没年不詳)は、摂津国八部郡西尻池村(現神戸市長田区)在住の画家で、当館の粉本を収集した武井伊右衛門(1845~1917)が晩年に記した回顧録の第20巻の記事によれば、京都に出て円山派の中島来章につき薫陶を受け、地元に帰っては当時兵庫津(現神戸市兵庫区)に居住していた百々広年にも学び、両師の一字をもらい広章と号した、明治6・7年(1873・1874)頃に60歳くらいで亡くなったとされます。摂津国の地誌『西摂大観』下巻(明治44年刊)収載の文久元年(1861)霜月改「兵庫市中諸名家独案内」の諸芸職之分にも「画師 廣章」が見えることから、現在その作品はほとんど残っていませんが、当時兵庫津周辺では知名の画家であったようです。
なお、本デジタルアーカイブ収載の作品の写作者(所蔵者)の多数に「岡田(広章)」と見えることからわかるように、当館収蔵の粉本の大半は、この岡田広章の所蔵品を、没後武井伊右衛門が譲り受けたものです。 |