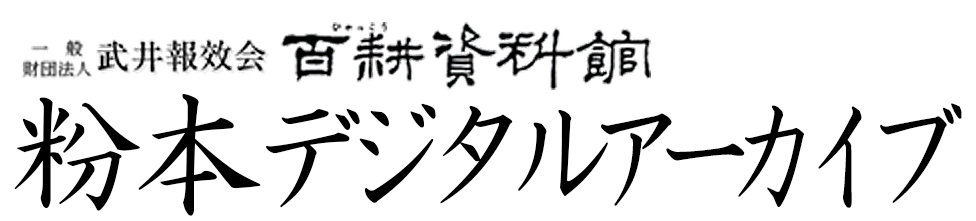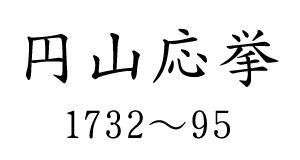 |
円山応挙(1732~95)は、姓は藤原のち源。字は仲選。通称は主水。初期には一嘯・夏雲・仙嶺などと号しましたが、明和3年(1766)応挙と改めました。丹波穴太村(現京都府亀岡市)の農家に生まれ、10代で京都に出て狩野派の画家石田幽汀に画を学びました。また、27歳の頃、尾張屋勘兵衛の店で眼鏡絵を描き、西洋画法を修得。33歳頃から円満院祐常門主と関わりを得て、その蔵画を模写、中国の古画や清画の写実技法を学び、しだいに写実を基本とした自然観照を画面に定着させる新画風「写生画」を確立しました。門人は非常に多く、その流れは円山派を形成しました。寛政2年(1790)の御所造営に一門を率いて障壁画制作にあたったのを始め、妙法院(京都市東山区)、金刀比羅宮(香川県琴平市)、大乗寺(兵庫県香美町)などに障壁画を残しています。 |
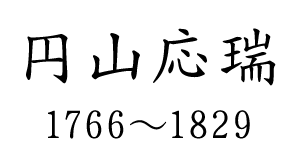 |
円山応瑞(1766~1829)は、姓は源。字は儀鳳。号は怡真堂。通称は初め右近のち主水。円山応挙の長男で、画を父に学び、円山家第2代となりました。応挙がプロデューサーを務めた天明7年(1787)の大乗寺(兵庫県香美町)の障壁画制作(第1次)にあたっては、応挙の最初期の門人たちに混じって最年少22歳で「遊鯉図」を担当し、寛政2年(1790)の御所造営にあたっても、25歳の若さで採用され、父や門人たちとともに障壁画を制作しています。その作風については「家法を守る」と評され、父応挙の画風を忠実に守り、特に花鳥を得意としました。多士済々の円山派を主宰し、一門の繁栄の基礎を築きました。 |
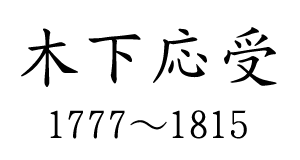 |
木下応受(1777~1815)は、字は君賚、号は水石。直一(直市)と称しました。円山応挙の三男(次男は夭折)で、母方の木下家の養子となりました。画を父応挙に学び、寛政7年(1795)の大乗寺の障壁画制作(第2次)では、10代後半にして孔雀の間・郭子儀の間・山水の間それぞれの長押と欄間の間に貼る画面に「遊亀図」を描いています。以後、兄応瑞と並んで大いに画壇で活躍しました。40歳に満たず早世したため、現存する作品は数少ないのですが、画技は兄応瑞を上回るものがあるともされています。 |
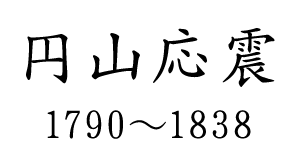 |
円山応震(1790~1838)は、円山応瑞の次男(応挙の三男木下応受の子で、応瑞の養子になったとする説もある)で、円山家第3代。字は仲恭。号は百里、星聚館、方壷子。主馬亮、主水と称しました。その詳しい伝記は知られていませんが、京都で刊行された文化人名録『平安人物志』の記載から、円山派の棟梁として文化~天保期(19世紀前半)に活躍したことが読み取れます。作風は、やや繊細に流れがちだった応瑞より力強い印象をうけるとされています。 |
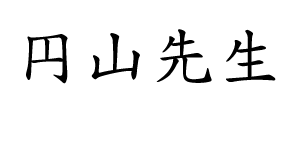 |
ここでは円山家第2代の円山応瑞(1766~1829)もしくは第3代の円山応震(1790~1838)。 |
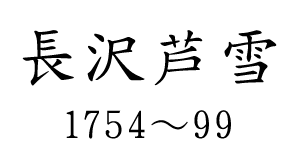 |
長沢芦雪(1754~99)は、名は正勝、魚。字は氷計、引裾。別号は于緝。山城(現京都府)淀藩士上杉和左衛門の子として生まれました。京に出て画を円山応挙に学びましたが、師の堅牢な写実から次第に脱却し、若くして奔放な独自の画風を確立した点では、円山派中異色の画家といえます。南紀に遊歴し、無量寺(現和歌山県串本市)、草堂寺(同白浜町)などに多くの障壁画を遺しました。寛政2年(1790)の御所造営では、御涼所上御間を担当する大役を果たし、寛政7年の大乗寺障壁画制作(第2次)でも一室を任され「群猿図」を描きましたが、45歳の若さで大坂で客死しました。 |
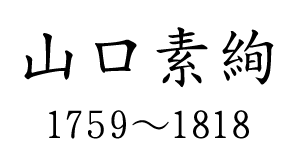 |
山口素絢(1759~1818)は、姓は橘、字は伯後、号は山斎。通称貫次郎または武次郎、のち可吉。布屋佐兵衛という京都の呉服商人の家の次男に生まれ、画を円山応挙に学びました。応挙がプロデューサーをつとめた寛政7年(1795)の大乗寺の障壁画制作(第2次)では「蛾蝶図」を描きました。また、寛政後期より書画展覧等の常連となりますが、平行して版本の絵にも手を染め、寛政11年の『倭人物画譜前篇』が人気を得、その後も数種の画譜を刊行しました。美人画の名手として知られ、とりわけ和美人に長じました。 |
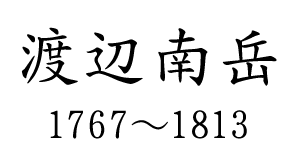 |
渡辺南岳(1767~1813)は、名は巌、字は維石、通称は猪三郎または小左衛門。京都の人とされますが、くわしい出自は不詳です。はじめ応挙の弟子である源琦に師事し、のち応挙に学んだとされ、さらには尾形光琳の作風を慕ってこれを折衷し、軽快な花鳥図や美人図を描きました。晩年は江戸に赴き、谷文晁や酒井抱一などと交わり、関東に円山派を伝えました。 |
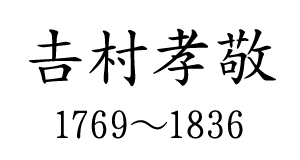 |
吉村孝敬(1769~1836)は、姓は源、名は孝敬、字は無辺もしくは無違、号は蘭陵のち龍泉、通称は要蔵。京都の人。応挙の門人吉村蘭洲の子で、自身も応挙に学びました。幼少のころから父とともに西本願寺19世宗主本如上人に仕え、同寺に代表的な作品を遺しています。総じて山水・花鳥に優れた作品が多く見られます。 |
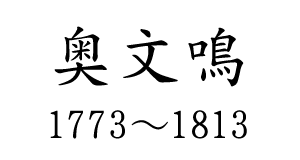 |
奥文鳴(1773~1813)は、姓は源、字は萬禩、伯熈。名は貞章のちに文鳴、号は六沈斎。はじめ源次郎のち順蔵と称しました。京都の産科医奥道栄(1750~1803)の子で、家業は弟が継ぎ、自身は応挙に学んで画家となりました。寛政2年(1790)の御所造営に加わり、応挙がプロデューサーをつとめた寛政7年(1795)の大乗寺の障壁画制作(第2次)では「藤花禽鳥図」を描きました。作風は彩色の美しさに定評があります。応挙の伝記『仙斎円山先生伝』の著者としても知られています。 |
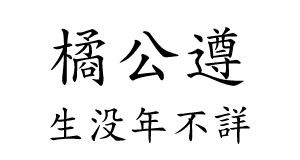 |
橘公遵(生没年不詳)は、和田氏、本姓は橘。名は公遵からのち公順に改めています。字は路卿、通称は金兵衛もしくは金次郎、醒堂と号しました。円山派の画家としてはこれまでほとんど注目されていない画家ですが、その技量や画風の広さは他の画家に見劣りしないと評価されています。 |
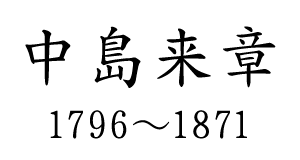 |
中島来章(1796~1871)は、姓は源。字は子慶。号は鶴江堂、春分斎、神通堂など。近江国(現滋賀県)の生まれ。円山派第2代の円山応瑞の門人とも、渡辺南岳や円山派第3代の応震に学ぶともいわれます。ともあれ、幕末の円山派を支えた中心画家として、正統派円山派の画法を伝え、山水・人物・花鳥など特定のジャンルにとどまらず画をこなしました。安政2年(1855)の御所造営にも参加し、障壁画を制作しています。四条派の横山清暉・塩川文麟、岸派の岸連山とともに幕末画壇の平安四名家の一人と称えられました。 |
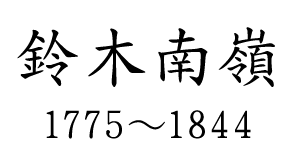 |
鈴木南嶺(1775~1844)は、名は順、字は子信、通称は猪三郎、観水軒とも号す。江戸の人。渡辺南岳の門に学び、人物花鳥をよくし、江戸円山派の画家として活躍しました。のち画をもって丹後(現京都府)田辺藩主牧野家に仕えました。 |
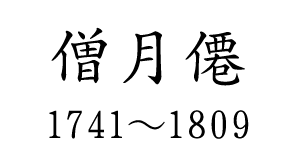 |
月僊(1741~1809)は、俗姓は丹家氏。名は玄瑞・元瑞。字は玉成。尾張(現愛知県)名古屋の醸造業の家に生まれました。7歳で得度して浄土宗の僧となり、十代で江戸増上寺にはいって定月大僧正より月僊の名を賜わったといわれます。仏門修行の傍ら、雲谷派に連なり「雪舟十二代画裔」と自称した桜井雪館に画を学びました。明和頃(1764~72)上洛して小松谷(現京都市東山区)に寄寓し、円山応挙の画にふれて強い影響を受け、さらに中国絵画を研究するなどして独自の画風を確立しました。のち知恩院57世檀誉貞現大僧正の依頼により、末寺の伊勢寂照寺(三重県伊勢市)の再興に赴き、その住職となって後半生をその地で送りました。
なお、月僊については、応挙や円山派の画家の直弟子となった明証はありませんが、一般に円山派とされることから、ここに収めました。 |
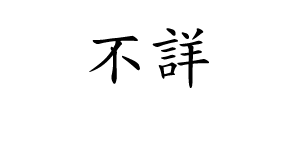 |
|