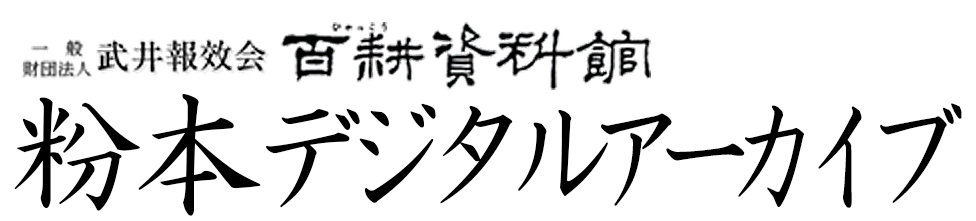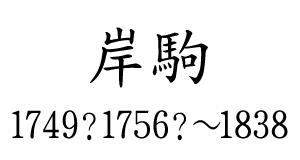 |
岸駒(1749?1756?~1838)は、姓は佐伯氏、岸氏、名を駒、昌明。字は賁然。号は華陽、可観堂、同功館、虎頭館、天開窟など。若い頃には蘭斎岸矩と称しました。生年については寛延2年(1749)説と宝暦6年(1756)説、出生地も金沢、高岡、富山などの説があって定説を見ません。定まった師はなく、独学で沈南蘋派を始めとする中国画、狩野派、洋風画を含む諸派の技法を研鑽したといわれ、京に上ってからは円山応挙にも師事して写生画を学んだらしいことが指摘されています。しかし、のち応挙と別れて「豪放」とされる独自の表現を確立、岸派の祖となりました。また、「虎の岸駒」と呼ばれ、迫真の虎の画で有名です。 |
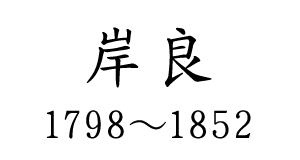 |
岸良(1798~1852)は、本姓は濱谷氏。名は五郎、昌良、字は士良、号は画雲楼、乗鶴など。雅楽助と称しました。京都の人。岸駒の長女貞の夫成が早死したため、その後婿として岸家の一員となりました。岸駒の豪放なスタイルや特徴的な筆運びを受け継ぐ一方、淡彩を用いた穏やかな花鳥画なども残しています。岸駒の長男で岸派第2代の岸岱とともに岸駒なきあとの岸派を支えました。 |
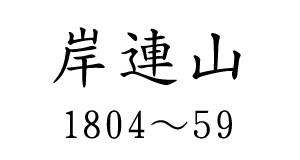 |
岸連山(1804~59)は、本姓は青木氏。名は徳、字は士道、士進、文進、号は万象桜。京都の人。岸駒の長女貞と岸成の娘春と結婚、岸姓を名乗り岸駒の養子となり、岸派第2代の岸岱に次ぐ実力者となりました。安政2年(1855)の御所造営に参加し、障壁画を描いています。その作品は、岸派の筆法を受け継いだ部分も見られますが、身近な花鳥を穏やかな色彩や筆法で描くことも多く、四条派への接近が見られます。幕末の京都画壇にあって、円山派の中島来章、四条派の塩川文麟・横山清暉とともに平安四名家といわれました。 |
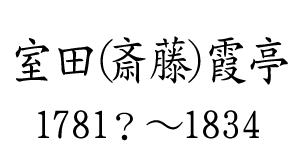 |
室田(斎藤)霞亭(1781?~1834)は、名は弘、字は光美。鉄山や耕筆園と号しました。室田家は代々兵庫津西宮内町(現神戸市兵庫区)で儒学と医業を家業とした名家ですが、霞亭自身はもともと長崎出身の画家斎藤雀亭の子で、同家には婿養子に入りました。江戸時代の兵庫津を代表する漢詩人の一人として知られ、書画にも優れました。画に関わっては、斎藤霞亭時代の文化6年(1809)8月、岸駒が金沢城二の丸御殿の障壁画制作のため下向した際、門人の一人として同道しており、また、当館に霞亭が岸駒の画を模写した粉本が残ることから、岸駒に師事したらしいことがわかります。 |
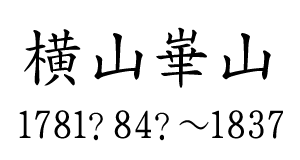 |
横山華山(1781?84?~1837)は、名は暉三また一章、号は舜明、舜朗、通称は主馬。越前出身説もありますが、一般には京都生まれとされます。北野天神社(現北野天満宮、京都市上京区)のほとりで織物業を営む横山家の分家の当主で画家でもあった横山惟馨の養子となり、画家として頭角を現しました。師は岸駒とされるものの、円山派の長沢芦雪や四条派の呉春、あるいは曽我蕭白などの筆意を学んだともいわれ、山水・人物・花鳥と画題により様式を使い分け、多彩な作品を描きました。 |
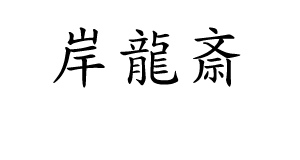 |
当館所蔵の粉本の中に、岸派らしい虎の画の模写が含まれることや、岸を名乗ることから、岸派に属する画家と考えられますが、伝記は不明です。なお、やはり粉本の中に「岸龍」による岸駒の画の模写が複数含まれていますが、この「岸龍」と「岸龍斎」が同一人物か否かは今のところ確定出来ません。 |
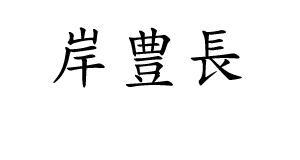 |
当館所蔵の粉本の中に、岸駒筆かと考えられる画を模写した粉本が含まれることや、岸を名乗ることから、岸派に属する画家と推定しましたが、伝記は不明です。 |