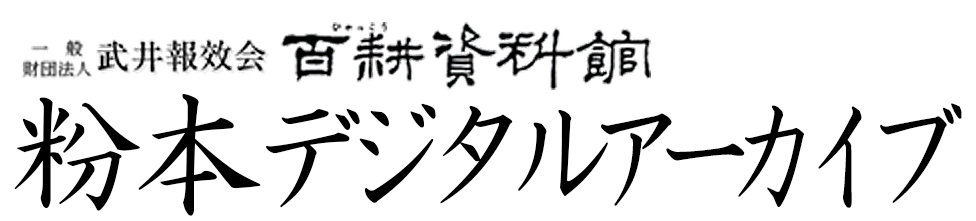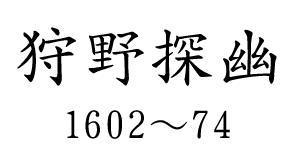 |
狩野探幽(1602~74)は、名は守信、采女。探幽斎と称し、別に白蓮子と号しました。幼時から天才を発揮、祖父永徳の再来と賞賛され、16歳で江戸に召されて幕府御用絵師となり、20歳で江戸城鍛治橋門外に屋敷を拝領、奥絵師鍛治橋狩野家の祖となりました。以後幕府の大造営事業に一門の総帥として参加、寛文2年(1662)には画家として最高位の法印に初めて叙されています。こうして探幽は、江戸狩野派の幕府御用絵師としての立場を絶対的なものとするとともに、桃山時代の豪壮な絵画様式に変わる瀟洒淡麗といわれる様式を生みだし、時代にあったこの様式が以後狩野派の規範として徹底されることになりました。探幽によって基盤が築かれた、この江戸を拠点とする狩野派を「江戸狩野」と呼びます。江戸時代を通じて、この江戸狩野が画壇の頂点に君臨しました。 |
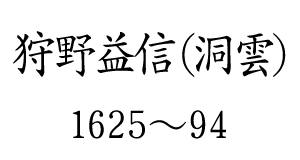 |
狩野益信(洞雲)(1625~94)は、幼名は山三郎。通称は采女。号は洞雲、宗深道人、松蔭子など。京都の彫金家後藤立乗の末子として生まれ、幼くして書を松花堂昭乗に学び、画を好みました。画技を見込まれて11歳で探幽の養子となりますが、実子が出来たため別家を興し、表絵師筆頭駿河台狩野家の始祖となりました。中橋狩野家の初代安信の娘を妻としています。寛永18年(1641)・承応3年(1654)・寛文2年(1662)の御所造営に参加し、特に延宝3年(1675)の御所造営では養父安信・義弟時信とともにその中核を担い、多くの障壁画を描きました。 |
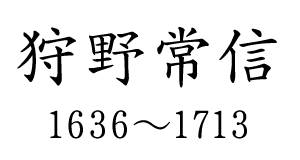 |
狩野常信(1636~1713)は、狩野尚信の長男で、尚信に始まる奥絵師竹川町(のち木挽町)狩野家の第2代。通称を右近、剃髪して養朴と号し、中務卿法印、古川叟、耕寛斎、青白斎など多くの号を持ちました。慶安3年(1650)に家督を継承、江戸城の障壁画や幕府による朝鮮や琉球への贈答用絵画を制作し、また承応3年(1654)・寛文2年(1662)・延宝3年(1675)・宝永5年(1708)の御所造営に参加しました。宝永5年の御所造営では、画家の仕事として最も格式の高い紫宸殿の「賢聖障子絵」を描き、翌6年には、かつて探幽しか叙されたことのない画家としての最高位である法印に叙されるなど、竹川町(のち木挽町)狩野家の隆盛の基礎を築きました。その画風は、探幽の画風に繊細さを加え、より装飾性に富んだ華やかな一面を見せるとされています。 |
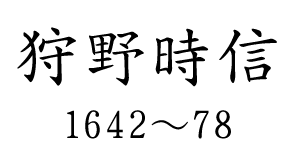 |
狩野時信(1642~78)は、狩野家の宗家にあたる奥絵師中橋狩野家の初代安信の長男で、通称は四郎次郎、のち右京と改めました。寛文2年(1662)の御所造営に父に従って参加し、延宝3年(1675)の御所造営では、父安信・義兄益信(洞雲)とともに障壁画制作の中核を担いました。しかし、延宝6年に父安信に先んじて37歳で早世したため、作品はあまり残されていません。なお、中橋狩野家はその子の主信が安信の養子となって継承しています。 |
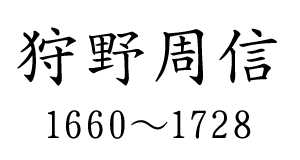 |
狩野周信(1660~1728)は、常信の長男(母は安信の次女)で、竹川町(のち木挽町)狩野家第3代。初名は右近。中務卿法印、如川、泰寓斎と号しました。正徳3年(1713)に家督を継承し、享保4年(1719)には法眼に叙せられました。奥絵師として江戸城の障壁画や朝鮮・琉球への贈答用屏風などを制作、また宝永5年(1708)の御所造営に参加しています。20~40代の伝記が不明で、伝存作品も多くありませんが、学習熱心で模写をよくこなしたらしいことのわかる、繊細優美な作品が見られます。 |
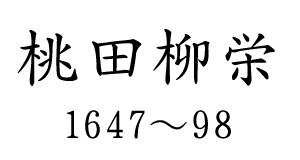 |
桃田柳栄(1647~98)は、名は守光、通称は武左衛門。幽香斎と号しました。和泉国(大阪府)の出身と伝えられ、画業のかたわら医業もなしたようですが、経歴はよくわかっていません。探幽門下四天王(他に久隅守景・神足常庵・尾形幽元あるいは鶴沢探山)の一人で、画風は探幽風を守りながらも柔和で彩色表現に優れるとされます。薩摩藩(現鹿児島県)島津家の御用絵師として召し抱えられたと伝えられます。 |
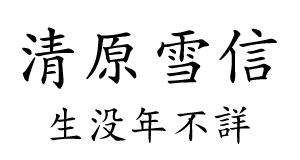 |
清原雪信(生没年不詳)は、名は雪。狩野派随一の女性画家として知られます。桃田柳栄・神足常庵・尾形幽元(あるいは鶴沢探山)とともに探幽門下四天王として知られる久隅守景と、探幽の姪国(神足常庵と探幽の妹鍋の娘)の間に生まれ、探幽門人の平野伊兵衛守清と結婚して(駆け落ちしたとも)京都に住んだといわれます。父守景と祖父探幽に画を学んだと考えられ、存命中より高い名声を得ていました。残された作品の多くは掛幅(掛け軸)で、障壁画の大作は少なく、また、画風は探幽に近く、女性らしいデリケートな彩色・タッチを持つ人物画・花鳥画に優品が見られます。 |
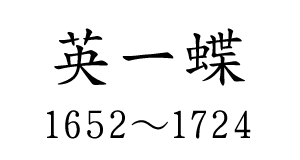 |
英一蝶(1652~1724)は、本姓は藤原、多賀氏。名は安雄のちに信香、字は君受、剃髪して朝湖と称しました。号は翠蓑翁、暁雲堂、北窓翁など多くの用例が知られます。伊勢(現三重県)亀山藩主石川侯の侍医多賀伯庵の子として京都に生まれ、15歳のころ江戸に下って奥絵師中橋狩野家の初代狩野安信に師事しましたが、のちに破門されたと伝えられます。松尾芭蕉に師事して俳諧にも長じ、画家としては多賀朝湖として知られましたが、元禄11年(1698)幕府の怒りに触れて三宅島に流され、宝永6年(1709)赦免されて江戸に戻って以降英一蝶を名乗りました。探幽の繊細な線質をうけつぎつつ、浮世絵の画題を取り込み、軽妙洒脱な都市風俗画の世界に新風を開きました。 |
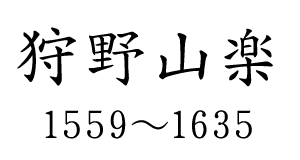 |
狩野山楽(1559~1635)は、名は光頼、幼名平三のち修理亮を名乗り、山楽と号しました。近江(現滋賀県)の戦国大名浅井長政の家臣木村永光の子。父は浅井家滅亡後秀吉に仕え、山楽は秀吉の推挙で狩野永徳の弟子となったといわれます。若年には永徳の絵画制作に従い、やがて狩野姓を許され、その豪壮な画風を引き継ぎ、永徳没後も有力門人として活躍しました。元和元年(1615)、大坂夏の陣で豊臣家が滅亡すると、戦後残党狩りの標的となりましたが、九死に一生を得たのちは、徳川家の仕事にも従事しています。ただし、狩野本家のように江戸に移って幕府御用絵師とはならず、京都に住んで養子の山雪らとともに制作を続けました。この山楽・山雪の家系は、代々京都で画業を引き継ぎ、のちに「京狩野」と呼ばれます。 |
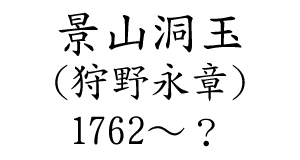 |
景山洞玉(1762~?)は、名は守俊。字は伯峯。号は洞玉。備後(現広島県)の出身と伝えられます。京狩野第8代狩野永俊の弟子で、のちに狩野姓と永章の名をもらい、狩野洞玉あるいは狩野永章と名乗りました。法眼に叙せられ、少なくとも70歳前後までは生存したようです。また、軽舟の号を持つ俳人としても知られていました。画家としては、江戸狩野の作風を身につけ、狩野元信などの正当な古狩野の作風を受け継ぐ一方、鶴沢派や円山派などの京都画壇の新しい動向もよく理解していたと評されています。 |
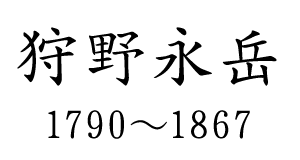 |
狩野永岳(1790~1867)は、字は公嶺。号は山梁、脱庵、晩翠。通称は縫殿助。初め泰助。景山洞玉(狩野永章)の子で、京狩野第8代狩野永俊の養子となり、第9代となりました。山楽の代に遡る桃山風の豪壮な画風を基本に、当時流行の四条派や文人画派、復古大和絵派などの画風を積極的に取り入れ、幕末の京都画壇の雄として名をはせました。安政2年(1855)の御所造営で多くの障壁画を制作するなど朝廷の御用を務めたほか、公家、寺院また彦根藩や紀州徳川家などの大名家の御用も務め、さらには富農や富商層にも需要層を広めています。 |
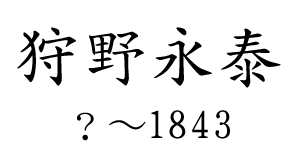 |
狩野永泰(?~1843)は、名は泰。字は東美。洞玉と号す。通称は式部。景山洞玉(狩野永章)の子で、狩野永岳の弟。父を継いで二代目景山洞玉を称したのち、京狩野家から狩野の姓と永泰の名をもらい、狩野永泰と名乗りました。狩野姓を得てのちは其同の名も用いています。父洞玉(永章)よりむしろ兄永岳の影響をうけ、また当時諸派で流行の画法をとりいれつつも、画面構成やモチーフに独自の端正さをもった作品を遺しました。なお、幕末の復古大和絵派の領袖として著名な冷泉為恭は永泰の三男です。 |
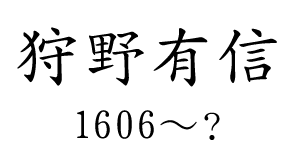 |
狩野有信(小原友閑斎、1606~?)は、明暦2年(1656)に佐賀藩のお抱えとなった絵師で、竹川町(のち木挽町)狩野家の第8代狩野栄信の次男朝岡興禎による画人伝『古画備考』に狩野派の門人として見え、探幽の門人ともいわれます。同書に「富士書キ」とあるように、富士山の画を得意としました。 |
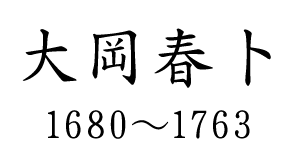 |
大岡春卜(1680~1763)は、名は愛菫。字は春卜。号は一翁、雪静斎、翠松、秀月、式部卿など。通称半七。大坂の人。幼少より画を好み、始め狩野派に入門したようですが、のち決まった師を持たず狩野派の筆法を研究、明清画も修めて一家を成し、高い画名を誇りました。享保5年(1720)以前に法橋、同20年には法眼に叙せられています。その画題は多彩で、また、肉筆画制作のかたわら、多数の絵手本(版本)の編集を手がけました。春卜は、同じく狩野派の門に学んだ橘守国と並んで、大坂画壇成立の立役者とも評されています。 |
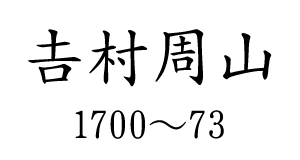 |
吉村周山(1700~73)は、名は充興。号は周山、探僊叟、探仙叟、探興斎。通称周次郎。大坂の人。狩野探幽の弟子鶴沢探山門下と伝えられる牲川充信に学び、一家を成してのちは大岡春卜と並び称され、法眼に叙されました。また、根付彫刻にも巧みであったといわれます。三宅春楼、中井竹山、中井履軒ら儒者・書画家との交友もあり、山水・人物画に独自の境地を開きました。 |
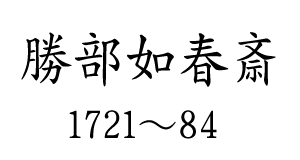 |
勝部如春斎(1721~84)は、字は兼寿のち典寿、通称は源蔵、号は初め容斎のち如春斎。西宮の酒造家雑喉屋勝部家の次男として生まれました。大坂の狩野派の絵師櫛橋栄春斎に学んだとされ、のち京摂の間に寓居し、その絵を求める者が多かったと伝えられます。明和元年(1764)には左大臣九条尚実より「如春斎」の号を下賜され、以降「台賜如春斎典寿」の落款を用いました。地元西宮に伝えられていたその作品の多くが戦災で失われましたが、現在も西宮を始め、尼崎・伊丹・池田などに若干の障壁画を含む作品が少なからず遺されています。 |
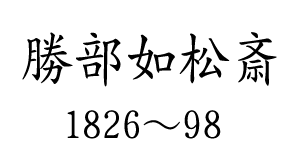 |
勝部如松斎(1826~98)は、字は典温、通称は源十郎。幼名安之允のち良介。勝部如春斎の兄源十郎兼方の玄孫。兼方の子八蔵(松容斎典運)、その子八蔵(栄春斎松操)と弟源之介(如真斎典昌・松貫)はいずれも絵を描いたとされるので、如春斎からの画統が続いていたと考えられます。 |
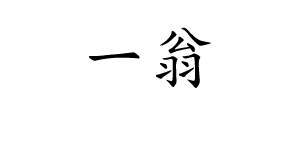 |
狩野派には、一翁を号した人物として、すでに解説した大岡春卜と狩野内膳(1560~1616)とがいます。春卜については、同人の解説参照。また、狩野内膳は、名は重郷、号は一翁。戦国大名荒木村重の家臣の子として生まれました。9歳のころ紀伊(現和歌山県)の根来寺密厳院に預けられましたが、生来画を好んだため、のちに大坂に出て探幽の曾祖父・狩野松栄に入門、天正15年(1587)に狩野姓を許されました。豊臣秀吉の信任あつくその御用を務めました。慶長9年(1604)の秀吉七回忌に行われた豊国社臨時大祭の模様を描いた「豊国祭礼図屏風」(豊国神社蔵)や「南蛮屏風」(神戸市立博物館蔵)などが代表作として知られます。 |
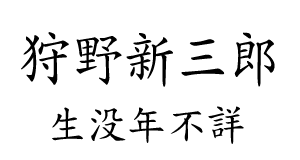 |
狩野新三郎については、元禄8年(1695)作の伊勢神宮の神宝を描いた「諸社御神宝図」(伊勢内外宮神宝式并神宝図五巻のうち。前田育徳会蔵)の筆者としても名が見えますが、くわしい伝記は不明です。 |
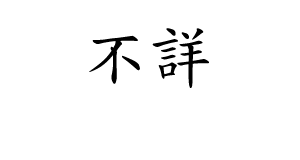 |
|