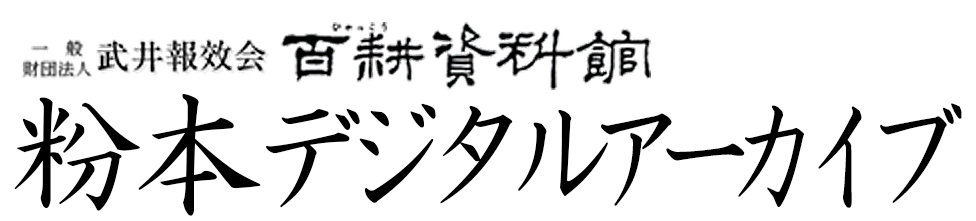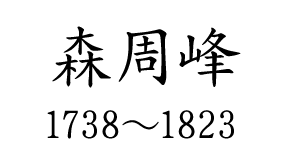 |
森周峯(1738~1823)は、名(または字)は貴信。号は周峯、鍾秀斎。文泰・林蔵とも称しました。生まれは西宮説・長崎説がありますが、大坂で活躍しました。画家森如閑斎の次男で、兄の陽信・弟の狙仙も画家。初め父に画の手ほどきを受けたと思われますが、のち狩野派の吉村周山に学んでいます。また、その後、大坂の狩野派出身の美人風俗画家月岡雪鼎についたとする史料もあります。安永6年(1777)頃法橋、寛政11年(1799)には法眼に叙され、寛政2年の御所造営にも画筆を揮うなど、大坂画壇の重鎮として知られました。弟狙仙とは対照的に伝統的な狩野派の描法を駆使して多彩なモチーフの画を残しています。 |
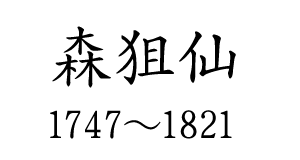 |
森狙仙(1747~1821)は、名は守象。字は叔牙。号は如寒斎、霊明庵。さらに初め祖仙と号しましたが、文化4年(1807)に狙仙に改めました。生まれは大坂説・西宮説・長崎説がありますが、いずれにせよ大坂で活躍しました。画家森如閑斎の三男で、兄の陽信・周峰も画家。兄とともに初め父に画の手ほどきを受けたのち、勝部如春斎から狩野派の技法を学びましたが、それにあきたらず、新しい時代の風潮として応挙に通じる写実的描写を試み、動物画に本領を発揮、特に猿の画を得意としたことで知られます。 |
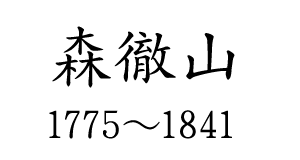 |
森徹山(1775~1841)は、名は守真、字は子玄または子真。通称文蔵。号は徹山。大坂の人。森周峰の実子で、狙山の養子となりました。絵を実父周峰・義父狙山に学んだのち、円山応挙にも師事しました。寛政7年(1795)の大乗寺障壁画制作(第2次)には、一門で最も若い21歳で参加し、長沢芦雪の「群猿図」の上の小壁を飾る「山雀図」を描いています。京都には住まず終生大坂で過ごし、円山派の画を大坂に広めました。晩年には熊本藩細川家にも仕えています。実父周峯から学んだ狩野派の画法に、養父狙仙譲りの動物写生と応挙の写実画法を加味し、独自の画風を確立。特に動物画を得意としました。 |
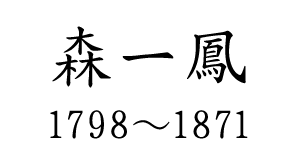 |
森一鳳(1798~1871)は、名は敬之、字は子交・子孝、通称は文平、播磨吉田村(現兵庫県内)の出身とされます。絵を森徹山に学び、のちに養子となって大坂を拠点に活躍しました。安政2年(1855)の御所造営に参加し、障壁画を制作しています。また、徹山同様熊本藩細川家に仕えました。徹山の写生画風をもとにしつつ、軽妙洒脱な感覚を盛り込み、とりわけ一鳳の描く藻刈船の画は「藻刈る一鳳」(儲かる一方)として求める者が多く、当時大いに流行したといいます。 |
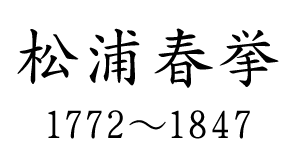 |
松浦春挙(1772~1847)は、幼名は亀八、のちに宇吉。通称は猪三郎・要人。名は依景、のちに重吉。別号に三桃、舜挙。阿波(現徳島県)の人。現小松島市の藍商人の家に生まれました。幼いころから画を好み、大坂に出て森狙仙に弟子入りして画家となりました。動物に巧みで、特に孔雀にすぐれました。 |