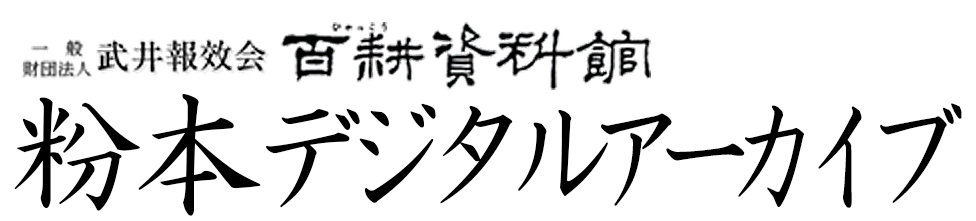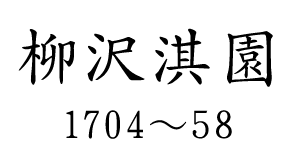 |
柳沢淇園(1704~58)は、名は貞貴、字は公美、号は玉桂・淇園。甲府藩主柳沢吉保の筆頭家老曾禰保格の次男。享保9年(1724)主家の転封にともない大和郡山(現奈良県大和郡山市)に移住、元服にあたっては第2代当主吉里より柳沢姓を許され、享保12年には一字を拝領、名を里恭と改め、柳里恭とも名乗っています。多芸多才で知られ、その教養は詩書画から仏典や医学・音楽に及びました。絵は8・9歳より学び、狩野派を批判し、長崎派の英元章(吉田秀雪)に師事、のち独学で中国の画論を修得、濃密な色彩の人物・花卉、墨竹などを描きました。祇園南海、彭城百川と並ぶ初期文人画家の一人として知られます。 |
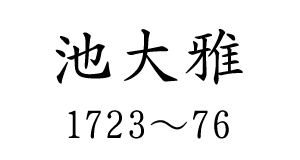 |
池大雅(1723~76)は、姓は池野。名は勤、無名。字は貸成、公敏。画号は大雅、霞樵、三岳道者、玉海など多数。京都の銀座役人の下役の子として生まれました。幼少より書において才能を発揮し、また黄檗山万福寺に出入りして中国文化と接触しました。絵は初期文人画の祇園南海や柳沢淇園らの影響のもと、中国の古画や『八種画譜』『芥子園画伝』などの画譜から学ぶ一方、広く日本の諸画派や西洋画にも学び、自由奔放な独自の画風を築きました。とりわけ風景画では、各地への遊歴で実景に触れた経験をもとに、遠近法も取り入れ、生き生きとした現実感あふれる空間を表現しました。与謝蕪村とともに、日本文人画の大成者といわれます。 |
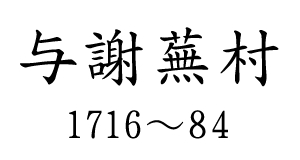 |
与謝蕪村(1716~84)は本姓は谷口氏または谷氏。名は信章、寅、字は春星。号は四明、朝滄、謝長庚、謝春星、謝寅など多数。蕪村は俳号です。摂津国東成郡毛馬村(現大阪市都島区)の富農に生まれ、20歳前後に江戸に下り、俳人早野巴人(夜半亭宋阿)に入門。師の没後、下総国結城(現茨城県結城市)など北関東の遊歴を経て、宝暦元年(1751)36歳の時上洛。その後丹後(現京都府)・讃岐(現香川県)に一時滞在しますが、京都を定住の地として俳諧と絵画制作に専念し、画俳ともに高い評価を受けました。画は独学で、狩野派ややまと絵、中国の南宗画・北宗画など諸派を学び、独自の画風を創造、美しい墨と淡彩による情趣ある山水画や、筆技の冴える水墨画を描きました。池大雅とならぶ日本の文人画の大成者とされます。 |
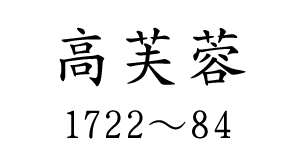 |
高芙蓉(1722~84)は、本姓は源、大島、名は孟彪、通称は逸記、字を孺皮。号は芙蓉、その他に三嶽道者、中嶽画史、氷壑山人、富岻山房など。甲斐国(現山梨県)出身。20歳頃京都に移住し、儒学、金石学、篆刻、書画を学び、特に篆刻と画で知られました。篆刻では秦漢の古印の復古を志して日本の刻風を一変させ、印聖と呼ばれました。画は宋元画を模した清楚な作風の山水画に長じました。池大雅とは、終生の友といった関係にありました。 |
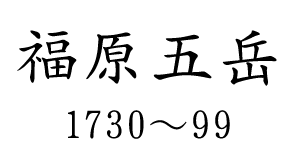 |
福原五岳(1730~99)は、名は元素、字は子絢、太初。号は五岳、玉峯、楽聖堂。通称大助。備後尾道(現広島県尾道市)出身。京で池大雅に学び、大坂に出て大雅の画風をひろめ、大坂文人画壇隆昌の先鞭をつけました。初期文人画家の一人である彭城百川以来の人物画の名手と謳われましたが、幅広い画題をこなし、山水画にも優品を残しました。また詩や書にもすぐれ、画家のみならず大坂の知識人の漢詩サークル・混沌社や大坂第一の漢学塾・懐徳堂のメンバーなどとも交流しました。 |
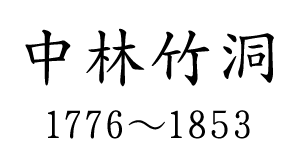 |
中林竹洞(1776~1853)は、名は成昌。字は伯明。号は竹洞、筆樵、痴翁など。通称は大助。名古屋の医家に生まれ、14歳で山田宮常に絵を学び、翌年から名古屋の豪商神谷天遊のもとに寄宿し、山本梅逸とともに同家所蔵の古画の模写で画技を磨きました。のち27歳で梅逸とともに京都に出て、画家として門戸を構えながら、中国元・明の古画を模写し、儒学や国学の研究に努め、文人画家として一家を成しました。山水画・花鳥画にすぐれ、特に瀟洒な山水画を得意としました。また、理論家としても知られ、画論のほか、儒学や国学の研究に基づいた国体論なども残しています。 |
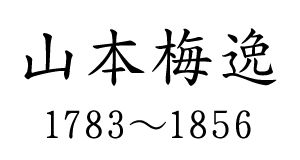 |
山本梅逸(1783~1856)は、名は親亮。字は明卿。号は梅逸、春園、梅華佚人、玉禅、天道外史、葵園など。通称卯年吉。名古屋の彫刻師の家に生まれ、幼少より画に秀で、山本蘭亭・張月樵などに師事したのち、名古屋の豪商神谷天遊のもとで中林竹洞とともに教育をうけました。その後20歳で竹洞とともに京都に上りますが、いったん各地を遊歴して文人画家としての画名を高め、天保3年(1832)頃再び上洛、以後京都で活動しました。安政元年(1854)名古屋に帰り、藩の御用絵師格となって士分に取り立てられました。梅逸の画風は、文人画に写生画の画風を取りこんだ独自の画風で、とりわけ花鳥画の名手として知られます。 |
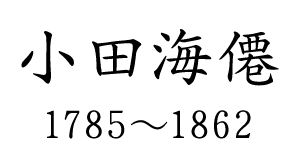 |
小田海僊(1785~1862)は、名ははじめ煥のち羸。通称は良平、字は巨海。号ははじめ南豊のち百谷、海僊など。長門国赤間関(現山口県下関市)出身。文化3年(1806)に上洛して、四条派の呉春に入門しました。南豊・百谷と号していた30代半ばまでは四条派流に描きますが、文化11年に儒学者・詩人の頼山陽に知遇を得てからは文人画へ傾倒し、山陽の助言で元や明の遺作を模しつつ、独自の文人画風を打ち出しました。文政元年(1818)からは5年間山陽とともに九州を遊歴。同7年には萩藩の御用絵師となっています。 |
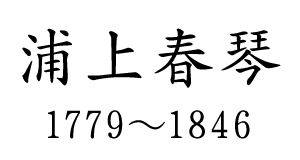 |
浦上春琴(1779~1846)は、姓は紀。名は選。通称喜一郎。字は伯挙・十千。号は春琴、睡菴・文鏡亭など。代表的な文人画家として知られる浦上玉堂の子として備前岡山(現岡山市)に生まれました。父に絵を学び、備前鴨方藩士であった父の脱藩にともない諸国を遍歴したのち、京都に居を構え、以後当地を拠点に活動。頼山陽や田能村竹田といった文人たちと交流し、京坂の文化人サークルに名を連ねました。春琴は、玉堂の独創的な画風とは異なり、清麗温雅な山水画・花鳥画を描き、生前は父以上の評価を得ていました。 |
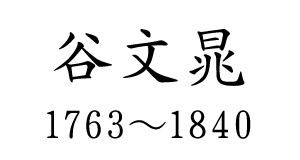 |
谷文晁(1763~1840)は、名は正安。字・号ともに文晁。通称文五郎または直右衛門。別号に写山楼・画学斎など。田安徳川家の家臣で漢詩人として著名であった谷麓谷の子として江戸に生まれ、長じては田安家に出仕し、同家出身の老中松平定信付として隠居まで仕えました。12歳で加藤文麗から狩野派の画を、18歳で渡辺玄対に明画を習いましたが、「八宗兼学」と評されるようにその学習態度は旺盛で、明清画を中心に中国・日本・西洋の画法を広く学び、関東文人画の大成者として知られます。山水画を中心に、花鳥画、肖像画、仏画など画域は広く、多くの著作も遺しました。また、画塾写山楼を営み、多くの後身を指導し、当時を代表する文化人として、多数の儒者・詩人・書画家などと交流しました。 |
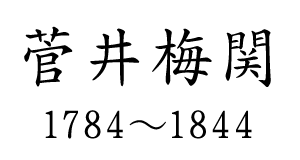 |
菅井梅関(1784~1844)は、名は岳輔・智義、字は正卿、通称善助・善五郎。号ははじめ東斎、のち梅館・梅関。奥州仙台(現宮城県仙台市)の出身。老舗茶舗の長男に生まれました。幼少より絵を好み、仙台藩絵師根本常南に絵を学びました。常南に画才を認められ、江戸に出て谷文晁に師事しましたがほどなく去り、京都、長崎で学び、とりわけ長崎では、来舶清人の江稼圃から書画の手ほどきをうけ、滞在は十年余に及びました。その後活動拠点を京坂に移し、頼山陽や田能村竹田、岡田半江らと交流し、画名を挙げました。特に自由で伸びやかな筆致の墨梅図が高く評価されました。40歳余で仙台に帰郷。不遇のうちに窮死しました。 |
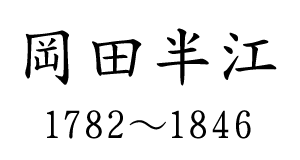 |
岡田半江(1782~1846)は、名は粛、字は子羽、通称卯左衛門のち彦兵衛。幼名を常吉といい、号は小米のち半江。別号に無戸、自適、寒山など。半江の父岡田米山人は、大坂で米屋を経営、また伊勢(現三重県)津藩藤堂家に大坂蔵屋敷下役として仕える一方、文人画家として活躍しました。半江は大坂で生まれたとされ、幼少から父より絵の手ほどきを受けました。父の没後は父同様に家業の米屋の繁盛に腐心し、藤堂家に仕える一方、文人画家として活動、頼山陽を始め、多くの文人・学者と交流しました。とりわけ40代で家業を子息に譲り、藤堂家も辞して書画三昧の隠逸生活に入って以後その画才の本領を発揮し、晩年には緻密な筆致で清澄感あふれる山水画風を確立。当時から高く評価されました。 |
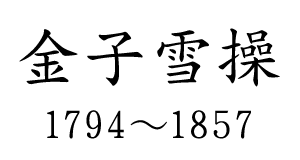 |
金子雪操(1794~1857)は、江戸の人。姓は犬塚、のち金子氏の養子になる。名は大美、字は不言または孟玉 、通称は六蔵。号は各半道人、有情痴者、塵海漁者など。幼少のころ伊勢(現三重県)長島藩主増山雪斎に仕えて絵の手ほどきを受け、雪操の号を授けられたといいます。致仕後、越後(現新潟県)の釧雲泉に山水画法、大窪詩仏に漢詩を学び、京都で書を修めました。のち大坂に住んで古画を研究し、知己を得た吹田村(現大阪府吹田市)の代官井内左門の招きで当地に8・9年間居寓。多くの作品を残し、再び大坂に戻りました。画風・画題は幅広く、特に文人画風の山水図が多く遺されています。 |
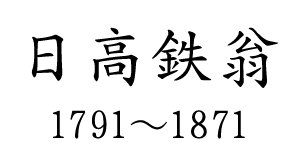 |
日高鉄翁(1791~1871)は、法名は鉄翁祖門、日高は俗姓。別号に明言・魚光・銕道人など。長崎銀屋町(現長崎市)の桶職人の子。11歳で父を亡くし、春徳寺の第13代住持玄翁和尚に養育されました。早くから画を好み、初め唐絵目利職の石崎融思に絵を学び、融思の没後は来泊清人の江稼圃につき文人画を研鑽しました。玄翁の没後、春徳寺の第14代住持となり、退隠後は雲竜寺に移り、書画禅三昧の日々を送っています。山水、四君子(蘭・竹・梅・菊)を善くし、特に墨蘭に優れました。木下逸雲、三浦梧門とともに長崎三大家と称されます。 |
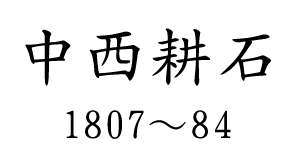 |
中西耕石(1807~84)は、名は寿。字は亀年。号は耕石、竹叟、筌岡など。筑前芦屋(現福岡県芦屋町)の人。京都に出て四条派の松村景文、のち文人画に傾倒後の小田海僊に師事しました。また大坂で篠崎小竹に漢学を学んで文人画の研究へと進み、幕末の文人画界で日根対山と並び称されました。維新後は京都を代表する文人画家として活躍、明治13年(1879)の京都府画学校(現京都市立芸大)設立に尽力し、同15年第1回内国絵画共進会で銅印を受賞するとともに、絵事功労褒状を受けました。 |
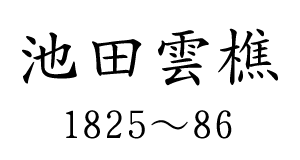 |
池田雲樵(1825~86)は、名は政敬。字は公維。別号に半仙など。伊賀山田郡喰代村(現三重県伊賀市)に生まれました。幼くして絵を好み、10歳で内海雲石に絵を学び、のち前田暢堂,中西耕石に師事して文人画を、斉藤拙堂に詩文を学びました。長じては伊勢(現三重県)津藩主藤堂侯に招かれ藩画師となっています。維新後、明治7年(1874)京都に移り、同13年京都府画学校(現京都市立芸大)出仕拝命。翌年南宗(文人画)の副教員となると,病没までその任を務めました。同15年第1回内国絵画共進会で賞状を受けました。 |
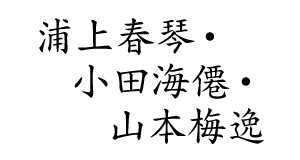 |
それぞれの画家の解説をご覧下さい。 |