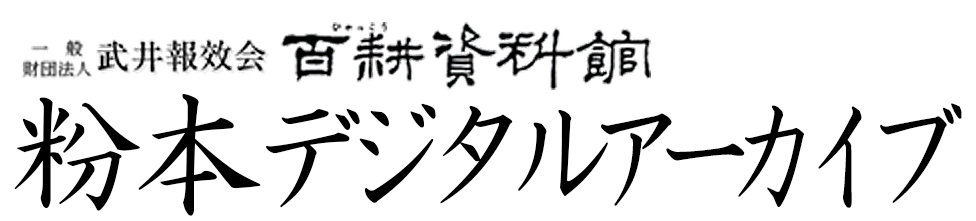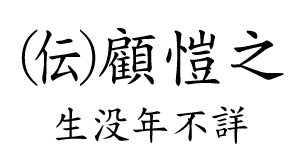 |
顧愷之(生没年不詳)は中国(東晋)の画家。字は長康。無錫(江蘇省)の人。多才で才絶、画絶、癡絶をもって三絶と称されました。興寧2年(364)、建康(南京)の瓦官寺北殿に維摩像を描いて名声を得ました。大司馬の桓温の参軍となって江陵、荊楚を遊歴。晩年は建康に帰り、義煕元年(405)年散騎常侍に任ぜられましたが、62歳で没しました。歴史始まって以来といわれたほどの天才で、特に肖像画、人物画に秀でました。真筆は現存しませんが、筆跡をうかがえるものとして、唐代の模写といわれる大英博物館所蔵の『女史箴図』や宋代の模写とされる『洛神賦図巻』(北京故宮博物院等)などがあります。 |
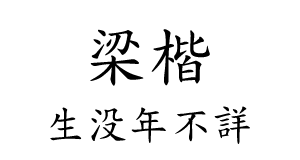 |
梁楷(生没年不詳)は中国(南宋中期)の画院画家。東平 (山東省) の人。嘉泰年間 (1201~04) に画院の最高位である待詔となり、金帯を賜わったが受けず、柱に掛けて帰ったといいます。酒を好み画院画家としては型破りな性格で梁風子 (狂人) と呼ばれました。道釈人物、山水等幅広い題材をこなし、院体風の細密な描法をよくする一方、白描画法と逸品画風(伝統的用筆によらない非写生的で粗放な筆墨法)を融合させた減筆の描法による人物画でも知られます。牧谿・玉瀾などとならんで室町時代以後の日本の水墨画壇に大きな影響を与えました。 |
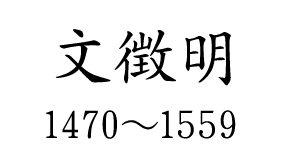 |
文徴明(1470~1559)は、中国(明代中期)の文人、書家、画家。初名は璧、字は徴明、のち徴仲と字しました。号は衡山、停雲生など。蘇州(江蘇省)の人。詩文を呉寛に、書を李応禎に学び、いずれも才能を表し、詩書画三絶と称されました。画は、沈周の影響を受け、山水・人物・花鳥・蘭竹画など幅広く、なかでも山水画は、趙孟頫と元末四大家を学び、簡潔な構図と淡彩・淡墨の細緻な描法を追求、沈周画とは異なる様式に到達しました。明四大家の一人。高潔、温和で謹直な性格から、祝允明、唐寅、王守らの多彩な文人たちの交友の中心人物となり、また、多くの文人画家を育成して「呉派」と呼ばれる画派を確立させました。 |
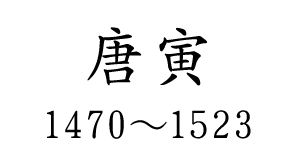 |
唐寅(1470~1523)は、中国(明代中期)の文人、画家。字は伯虎、子畏、号は六如居士、桃花庵主、逃禅仙吏、魯国唐生など。蘇州(江蘇省)の人。弘治11年(1498)の郷試に首席となりましたが、翌年の会試で不正事件に連座して投獄され、釈放後は蘇州を中心に放恣な生活を送り、自ら江南第一風流才子とも称しました。同郷の画家張霊、書家祝允明、文徴明などと親しく、詩文書画をよくし、当時の蘇州を代表する文人でした。画ははじめ院体画の流れを汲む周臣に師事、さらに南宋画院の李唐を学びましたが、のちには南宗画の要素も取り入れました。山水・人物・花鳥ともにすぐれ、一家をなしました。明四大家の一人。 |
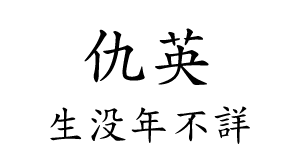 |
仇英(生没年不詳)は中国(明代中期)の画家。字は実父、号は十洲。太倉(江蘇省)の人で、蘇州(江蘇省)に移居しました。はじめ建築の装飾をほどこす民間画工であったといわれます。周臣に絵を習い、唐・宋の名跡を臨模して一家を成しました。人物、鳥獣、山林、楼閣、車馬など多くの画題を描きましたが、とくに風俗的な人物、美人画に名声があり、明四大家の一人として称えられます。市井の職業画家としては珍しく蘇州の文人画壇とも交渉があり、ことに文徴明の庇護を受けたと思われ、徴明ら呉派の文人画家との相互の影響が認められます。 |
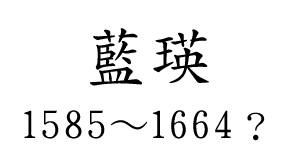 |
藍瑛(1585~1664?)は中国(明末・清初)の画家。字は田叔、号を研民、東閣老農、石頭陀など。杭州(浙江省)の人。初め地元で画を学びますが、それに飽き足らず江南の各地に遊学、当時江南随一の文人であった董其昌や陳継儒に宋・元の画法と文人画の理念を学び、晩年に杭州に帰って大規模な工房を構えて長寿を保ち、多くの弟子を育てました。藍瑛は、杭州の伝統的な浙派の様式に、江南の地で学んだ文人画風を取り入れ、新しい画風(武林派)を生み出しました。 |
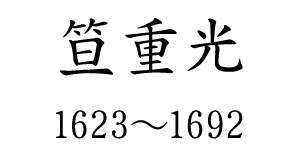 |
笪重光(1623~1692)は、中国(清代初期)の文人、書家、画家。句容(江蘇省)の人(一説に同省丹徒の人とも)。字は在辛または在莘、号は江上外史、鬱岡掃葉道人など。順治9年(1652)科挙に及第し進士となり、官は刑部郎中より湖広道監察御史となりました。剛直な性格で、その直言は人々を畏れさせたといいます。詩文書画にすべてに巧みで、鑑賞にも長じました。書は姜宸英、汪士鋐、何焯とともに四大家と称され、画は山水蘭竹を得意とし、惲寿平、王翬と交友がありました。 |
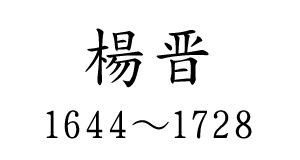 |
楊晋(1644~1728)は、中国(清代初期)の画家。清代初期の正統派の6人の大家「四王呉惲」の一人で画聖と呼ばれた王翬(1632~1717)の高弟。王翬と同じ常塾(江蘇省)の出身。字は子鶴、号は西亭。山水画をよくし、王翬とともに「康煕帝南巡図」12巻を描いており、王翬との合作が多く見られます。 |
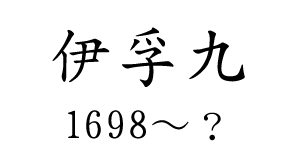 |
伊孚九(1698~?)は、江戸時代に来日した中国(清代)の画家(来舶画人と呼ばれる)。名は海、号は莘野、莘野耕史、也堂など。孚九は字。山塘(江蘇省)の人。本業は商人で、享保5年(1720)初来日し、以後享保11年から延享4年(1747)まで6回の渡来が知られます。商人でしたが、詩文書画にすぐれ、長崎に来た文人・画人と交遊しました。画は特に山水をよくし、その淡々とした味は来舶四大家(来舶画人を代表する4人の画家。伊孚九、張秋谷、費漢源、江稼圃。異説あり)を始め来舶画人の山水画の中でも別格とされます。長崎では清水伯民が孚九に学び、池大雅・野呂介石が私淑するなど、日本文人画に大きな影響を与えました。 |
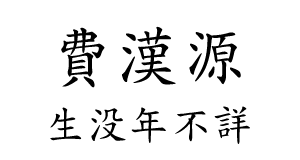 |
費漢源(生没年不詳)は、江戸時代に来日した中国(清代)の画家(来舶画人)。名は瀾、漢源は字。号は浩然。呉興県(浙江省)の人。享保19年(1734)以来、20年以上にわたり貿易商としてしばしば来日しています。本業は商人でしたが、山水・花卉・人物図などを得意とし、来舶四大家に数えられることもあります。建部綾足や若芝喜左衛門・楊利藤太などに画法を伝授しました。 |
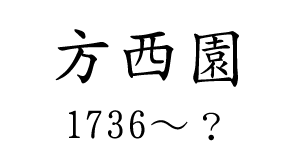 |
方西園(1736~?)は、江戸時代に来日した中国(清代)の画家(来舶画人)。福建、新安(江蘇省)、安徽寧国府旌徳県と出身地には諸説あります。名は済、字は巨川・巨済、号は西園。初来日の年も明和元年(1764)と安永元年(1772)の二説あります。その後安永~寛政年間(1772~1801)に何度か来日。安永9年(1780)には安房国千倉(現千葉県南房総市)に漂着、長崎に送還の途中富士山を写し、故国で賞されたといいます。本業は商人でしたが、画は周西山を師とし、水墨の山水・花卉画をよくし、その特色ある筆法は谷文晁、渡辺崋山などに影響を与えました。長崎においては真村蘆江がその画法を学びました。 |
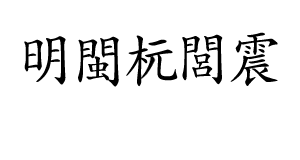 |
不詳。調査中です。 |
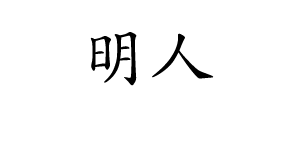 |
個人名は不詳。 |
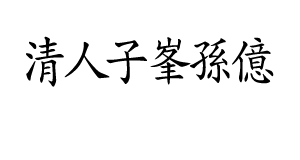 |
不詳。調査中です。 |
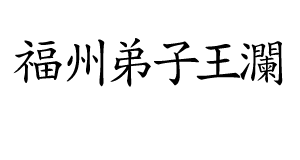 |
不詳。調査中です。 |